小学生からのゲームクリエイターが選ぶ、システムが美しいゲーム3選
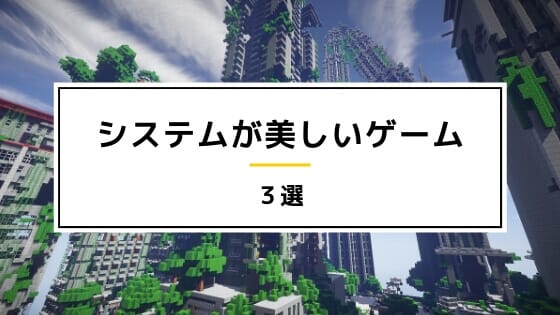
私は小学生の頃からゲームを作っていたドラレプです!
物心ついた頃からずっとゲームを作っていたので、自然と「なんでこのゲームはこうなってるんだろう、面白いんだろう」と考える人生を送っていました。
未成年の素人ながら、いっちょまえに他のゲームを「同業者」や「ライバル」として見ていたんだと思います。
その中で、『これは美しすぎる』と感じたゲームが3つあります。
奇をてらったものでもなく本気の紹介なので、ゲームのタイトルだけ見て「いや、当たり前だろ」と思う方もいるかもしれません。
しかしそれらのゲームがなぜすごいかを、全身全霊を込めて、持論たっぷりでお届けします!!
マインクラフト
はい、誰もが納得するだろうし、「今更マインクラフト紹介するの?」って感じですね。
これの凄さはもう数字が証明していて、世界のゲームの売り上げでテトリスに次ぐ第2位です。
販売からの期間を考えると、もはや歴史上世界一売れたゲームになるのももうすぐじゃないでしょうか。
これだけ売れたゲームが面白いのは説明するまでもないですね。
しかし、これのなにがすごいかって、ゲームデザインがもう美しいんです!
海外のゲームはオブジェクティブでシステム思考的
わけわからない横文字になってますが、海外のゲームってこういうものが多いんですよ。
- 人や物があり、それらは独立して動きが規定されています。
- それらが世界に放たれます。
- 世界にはルールがあり、そのルールのもとで人や物は独立して動いています。
- プレイヤーは世界や人、物に対してなんらかのアクションを起こすことで、目的を達成します。
おそらくわからないと思うので、例を紹介していきますね。
自由度のかたまり、「ザ・テーマパーク」
ザ・テーマパークという不朽の名作があります。
これはその名のとおり遊園地を経営するゲームですが、まさに上に書いたゲームデザインになっています。
プレイヤーはテーマパークに木や道、ショップや遊具と言った「モノ」を配置していくんですね。
そうすると、その「モノ」に合わせて、遊園地に遊びに来た人がそれぞれ動き回ります。
これのなにが面白いかって、自由に動き回るそれぞれの人に対して、なんでもできるということなんです。
- 道のあるところにしか人は動けないので、人が来たあと道を消して閉じ込められる。
- お客が並んでるときに値段を釣り上げて法外な値段で買わせられる。
- テーマパークの入り口を封鎖して、人が入り口に溜まったところで入場料を釣り上げられる。
むずかしくいうと、独立したモノや人の相互作用によって世界が成り立っているので、その組み合わせの数だけ可能性があるということなんです。
たとえばの話なのに長くなりましたが、本当にオススメのゲームです。
日本だと、「勇者のくせに生意気だ」
日本の例だと、「勇者のくせに生意気だ」がこういったデザインをしています。
このゲームは、簡単にまとめると次のようなゲームです。
- 穴を掘って、養分を生成する。
- 養分からモンスターが生まれる。
- モンスターを使って、侵入してくる勇者を倒す。
これだと「穴ほってモンスター作るだけ?」という感じです。
しかし、モンスターには生態系があるため、強いモンスターだけを増やし続けても生態系が崩れすぐに死滅してしまうんです。
自由に動き回るモンスターのエサを枯らさないように、生態系を維持しながら勇者を倒す必要があるわけです。
こういうゲームデザインが良いというわけではなく、あくまでデザインの1つでしかありません。
特にこういうゲームは可能性が無数にあるぶん、調整が難しいんです。
ゲームバランスは難しすぎず、簡単すぎないのが最適ですよね。
自由度が高すぎると、それをゲームの最初から最後まで維持するのが難しいんです。
逆にいえば、それを越えられたものはめちゃくちゃ面白いゲームになります。
最小のルールでプレイヤーの動きを規定する、マインクラフト
さて、マインクラフトは何がすごいかというと、最小のルールでプレイヤーの動きを規定しているからです!
私たち人は、家を作り、昼は家から出て仕事に行き、夜は家に帰り眠りにつきますよね。
マインクラフトは「プレイヤーは自然と家を作る」し、「プレイヤーは自然と家に明かりを照らす」し、「プレイヤーは自然と暗闇を避ける」し、「プレイヤーは自然と夜は家に篭る」んです!
しかも、次の2つのルールだけで、それらの行動を促しているんです!
- 暗いところにはモンスターが湧く。
- 夜は世界が暗くなる。
つまり、プレイヤーは夜モンスターにやられないように明かりが灯った空間(家)を作り、夜をこすわけです!!
したがって家も、家というオブジェクトがあるわけじゃありません。
モンスターが入ってこなくて、モンスターが湧かないような、明かりがある閉鎖された空間は全て家と言えるんです。
ビルダーズとマインクラフトの対比
個人的に対比として面白かったのが、日本版マインクラフトと言えるドラゴンクエストビルダーズです。
町はこれだっていうのが決まっていて、「家」になる条件が決まっていて、プレイヤーは物語に沿って動いていきます。
まさにガチガチにプレイヤーの行動を規定した日本的ゲームです。
どちらが良い悪いの話ではありませんが、普通にゲームを作ったら日本的になるのが自然だと思います。
- 家を建てるコマンドを選ぶと、家ができる
- 家の中はモンスターが湧かない
しかしマインクラフトは、家という概念を特別に定義することなく、「2つのルールだけで」作り出しているんです!
私にはこれが無駄がなく洗練されたゲームシステムに見えてなりません。
人々は現実世界と同じ行動をとる
同じように、数あるプレイ動画を見ていて、まさに無人島に降り立った人と同じような行動を皆さんが取っていることに、鳥肌が立ちました。
- 家の場所が分かるように、目印の高台をつけて遠くから見えるように明かりを灯す
- 地形に名前をつけて覚える
- 装備を整えて、洞窟に潜る
人は自然と家を作り、地形に名前をつけながら島を開拓し、素材を集め物を作り、家に帰って眠りにつくんです!
洞窟も、洞窟という概念自体がゲームにありません。
ただランダムに生成された地形にたまたま穴が開いただけで、人はそれを洞窟と認識しているだけです。
そして深い位置には鉱石があり、暗いところにモンスターが湧くため、プレイヤーはモンスターにやられないように装備を整え、アイテムを集めるために洞窟に潜るんです。
この現実世界を最小のルールで再現したと言っても過言ではありません。
無駄がない物は洗練された美しさがあります。
したがって私は、マインクラフトは世界一美しいゲームだと思っています!
ポケットモンスター
ゲームの説明はいらないですね。
早速、理由を説明していきます。
面白いゲームを作るための3大法則「選択する」「成長する」「集める」
私が思う面白いゲームを作るための3大法則が次の3つです。
- 選択する
- 成長する
- 集める
まず、これらについて説明していきます。
そもそもゲームとは何か
ゲームと映画と小説の違いはなんだと思いますか?
結局のところ、どれもエンターテイメントであって、その表現方法の違いでしかありません。
映画は「映像と音」のエンターテイメントで、小説は「文章」のエンターテイメントです。
そしてゲームは何かというと「プレイヤーが能動的に干渉できる」という点が他との違いです。
たとえばサウンドノベルというゲームは、基本は小説です。
しかし途中で選択肢が出てきて、それをプレイヤーが選択することで小説のストーリーが変わっていきます。
逆に言えば、プレイヤーが干渉できないのであれば、それは小説という形で出せば良いはずです。
クリエイターが自分の作品を作りたいというときに、小説家は小説、映画監督は映画というように考えがちです。
しかしフラットに表現方法の1つとして捉えると、プレイヤーに能動的に作品に干渉させるための手段としてゲームという形を選ぶということになります。
「選択する」ができて初めてゲームになる
「プレイヤーが能動的に干渉する」とは、「選択する」ということです。
つまりゲームはプレイヤーが「選択」できることで初めて成り立つと言えます。
アクションゲームも、進む方向やジャンプといった選択肢から選んでいると言えますよね。
全てのゲームには選択が含まれています。
「良い選択肢」と「悪い選択肢」
しかし選択が含まれれば面白いゲームになるわけではありません。
「1+1はなに?」なんて選択が無限に続いたとして、面白いですか?
選択は、どれが正解か分からないようなほどよい選択肢がないと、むしろ面倒な作業になってしまうんです。
これが面白いゲームを作るにあたって難しいポイントです。
たとえば、「あーアイテム集めの周回ダルいなー」っていうのはまさにこれです。
ほどよい難易度の選択はあった方が良いけど、簡単すぎる選択はむしろ面倒なだけです。
あればあるほどつまらないゲームになってしまうのです。
「レベルを上げて物理で殴れば良い」と呼ばれるクソゲーがあります。
これは攻撃コマンドが強すぎて「選択」が機能してないからこその批判です。
「悪い選択肢」を避けるためには?
では、どうすれば悪い選択肢をさけられるでしょうか。
選択が簡単になりすぎる例としてあるのが、プレイヤーが強くなりすぎて、難易度が下がりすぎてしまうケースです。
たとえばRPGで終盤に序盤のダンジョンに潜り直したら、モンスター出るたびに面倒だと思うでしょう。
戦うボタンを連打するだけですからね。
そのため、次のような対策が考えられます。
- 「ルーラ」のように瞬間的に移動できるする。
- 「自分より弱いモンスターが出なくするような魔法やアイテムを作る。
- 「終盤手に入る鍵」や「技」などを使って、クリア後はショートカットできるようにする。
ほかにも、プレイヤーの強さに合わせて難易度をあげていくという方法もあります。
ただこれはプレイヤーが強くなる意味が失われてしまうこともあるため、一長一短です。
あと選択を難しくする方法として、時間制約をつけるという方法もあります。
まさにアクションゲームは時間制約のついた簡単な選択の連続です。
目の前にモンスターがいたらジャンプをするのが正解だとすぐに分かることです。
しかし時間制約がつくことでそれが難しくなります。
つまりアクションゲームは、「悪い選択肢」を、時間制約をつけることで「良い選択肢」に変えてるゲームです。
快感物質をドバドバ出す「成長する」
選択の次が成長です。
成長は、プレイヤー自体のスキルが向上することもあれば、ゲーム内の数値が上がることもあります。
また、できることが増えることも成長と言えるでしょう。
成長するとドーパミンという快感物質がドバドバ出るため、それを体感できるゲームが面白いのは人の摂理と言えます。
「成長する」の注意点
注意点として、現代はドーパミンが出るものに溢れすぎていて、並大抵のものじゃ反応しなくなってきているという点があるます。
ようするに、すぐに成長を体感できるものじゃないと辞めちゃうってことです。
そう考えると、「プレイヤー自体のスキルが上がる」速度はどうしても遅いです。
アクションゲーム系、シューティングゲームや格闘ゲームなどがそうですね。
最近そういったゲームの人気が過去より落ちてきている要因も、現代人がドーパミン慣れしてることがあると思っています。
プレイヤースキルの「成長する」を数値でサポート
そのため、ゲームをデザインする際はプレイヤーの成長だけに頼らず数値的に上がる要素も付け加えるのがオススメです。
アクション性のあるゲームでも、プレイすればするほど強くなってくようにするというわけです。
たとえばモンスターハンターとかがそんな感じですね。
強くなってダンジョンをクリアしやすくなるというだけでなく、なにか要素が解放されるとかでも良いでしょう。
プレイヤースキルの「成長する」を記憶でサポート
あとは覚えゲーにするという方法もあります。
「ここは穴があるから避けよう」というだけであれば、2度目は失敗しません。
テクニックの成長じゃなくて経験したかどうかなので、すぐに成長を実感できるわけですね。
「集める」
人は何かを集めるのが大好きです。
「伝説の武器」であったり、「全ミッション達成」であったり、「全ての仲間」であったり、何かとコンプリートしたがる人は多くいます。
ただこれについては人によるため、必須な要素というわけではありません。
しかし集めるのが大好きな人もいるため、面白いゲームに切り捨てられない要素です。
これをゲーム内容を壊さずに作る方法が「称号」や「ミッション」で、最近は多用されていますね。
「ボスを3ターン以内に倒せ!」などをたくさん用意するだけで、「なんとなく集まってる感」を作り出すことができます。
約束された面白いゲーム「ポケモン」
これ全部を満たしていないといけないわけではなく、人それぞれ好みがあり、それぞれの要素の強いゲームを好みます。
とはいえ、面白いと言われるゲームはこの要素の多くを、良い形で満たしているものが多いです。
たとえばガチャ系のソーシャルゲームは、テンプレだけでこれを満たせます。
- カードを選んでデッキを組む
- カードを成長させる
- カードを集める
これを満たしているものが多ければ多いほど、より多くの人のニーズにマッチして、万人受けしやすいゲームになるわけです。
とはいえどれもあれば良いってわけじゃありません。
バランス感が難しく、難しすぎる選択肢が続くゲームもダメだし、成長するけど成長速度が遅いゲームもダメなんです。
そしてポケモンは、この3つ全てを、高いレベルで満たしているゲームだと思ってます!
特に数に制限をつけることによって、「選ぶ」の範囲を増やしているのが素晴らしいと思います。
- 3匹のポケモンから1つ選ぶ。
- 覚える技を4つ選ぶ。
- パーティーに入れるポケモンを6体を選ぶ。
- 努力値の割り振り先を選ぶ。
- イーブイの進化先を選ぶ。
- わざマシンを使う先を選ぶ。
- ポケモンに持たせる道具を選ぶ。
- ポケモンの特性を選ぶ。
- …
個々の要素だけ見ると、今となっては類似品も多くなってきて目新しいものではなくなってきてしまいました。
そのため今、他と比べても最高のゲームとは言えないかもしれません。
しかし、これだけ綺麗に3大要素を満たすゲームを作ったのはポケモンが最初だと確信しています。
アールエス
3作目はアールエスです。
これはアンディーメンテさんの作ったフリーのRPGゲームで、「何年もやっている人がいる」不朽のやり込みゲーです。
これも先ほどの面白いゲームの3大要素を満たしているゲームです。
しかしそれだけでなく、特にこのゲームがすごいと思ったのは「緊張」と「緩和」のデザインです。
面白いゲームを作るための「緊張」と「緩和」
元ネタは落語家の桂枝雀が唱えたもので、緊張の緩和が笑いを生むとする理論です。
これはゲームにも当てはまると思っていて、具体的な例でいうと「ダンジョン」と「街」です。
基本的にダンジョンに潜るのはストレスです。
早く出たいと思う一方で、これから解放されることや、成長によってこのストレスを減らすことがゲームにおける快感でもあります。
つまり必要悪ということです。
街はまさにストレスから解放される瞬間です。
そして同時に、報酬がもらえる瞬間でもあります。
報酬とは、「お金で武器を買って強くなる」「仲間が増える」「ストーリーが進む」といったものです。
ゲームは、「ストレスが与えられ」「そのストレスから解放されて報酬をもらう」の繰り返しとも言えるでしょう。
「緊張」と「緩和」のバランスが最高なアールエス
この「緊張」と「緩和」を最高に作り上げているのがアールエスです。
簡単にいうと、街でできることが沢山あるんです。
たとえば「ジョブチェンジ」「スキルの変更」「パーティー変更」「装備付け替え」「アイテム購入」といったベタなものから、「アイテムの合成」「パン屋の経営」「アイテム生成」など、書いたらきりがないくらい出来ることがあります。
つまりダンジョンから帰ってくるたびに、「パン売れてるかな?」「新しいアイテム合成できるかな?」と報酬に満ちあふれているわけです。
その上で、ダンジョンが常に死と隣りあわせのハラハラな難易度なんです。
ダンジョンも出たり入ったりしてもダメで、まともな報酬を得るためにはある程度潜る必要があります。
ワンミスで負けるようなバランス感のなかでダンジョンに潜り、長い苦労の先で沢山の報酬がもらえるため、緩急がすごいんです!
ゲームシステムだけ見たら、「合成」だの「ジョブチェンジ」だの、よく見る人気システムを詰め込みましたって感じかもしれません。
正直、システム的な目新しさはないでしょう。
しかしそれらを繊細にまとめ上げ、常に面白い緊張感と開放感を保ち続けているゲームで、アールエス以上のものを見たことがありません。
同じ理由で素晴らしいと思ってるのがTactical Chronicleで、こちらも名作なので紹介だけしておきます。
おわりに
熱意で書いた文章なのでまとまっていませんが、全身全霊を込めて3つのゲームを紹介しました。
単なる紹介ではなくマニアックな内容になってしまいましたが、これらのゲームを見る目が変わってくれたら幸いです!