役割の固定化が生む組織の問題と改善策
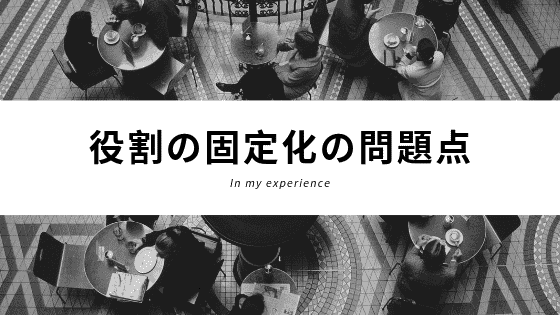
フリーランスで活動していると、色々な組織を目にします。
その中には、担当や役割を決め、その線引き以上には踏み入らないような文化の組織もあります。
もちろん作業できる能力を持ってないと前提に立てないため、職種による違いはあって当然です。
しかし同じ職種の同じ開発においてもチームが分かれ、チーム内で「ここはAさん」「ここはBさん」と決めていきます。
そんな組織に起こる「やっぱこうなるよなぁ」と思った問題点と、改善案について考察していきます。
役割が固定化した組織の問題点
役割が固定化した組織の問題点についてまとめるとこのような感じになります。
| 問題点 | 例 |
|---|---|
| 他責の念が生まれる | ・自分の仕事が進まないのはあの人が早く作ってくれないからだ! |
| 限定合理性が生まれる | ・あと10人で営業チームの目標達成できるんで、開発チームはキャンペーンの開発を優先してください。 |
| 属人性が強まる | ・Aさんの作業が終わるまで私の作業ができません。 ・Bさんが退職したので誰も手をつけられません。 |
| 仕事をしないほうがメリットがある | ・あなたの仕事範囲で問題起きたので、ここ全部直しておいてください。 ・Aさんもう仕事終わったみたいだからこれもAさんにやらせよう |
| 視野が広がらない | ・多分簡単だと思うんで、この画面のバックエンドの実装1日で終わりますよね? |
| 成長につながらない | ・ほかの人が何してるのか、どんな方法でやってるかわからないので、全て自己流です。 |
| コンフォートゾーンに逃げやすい | ・管理画面は私がやるのでほかの人は触らなくて大丈夫です。 |
| 受け身になる | ・バグ起きてましたけど自分の作業範囲じゃなかったのでスルーしてました。 ・振られたタスク全て終わったので、今日は帰ります。 |
それぞれ見ていきましょう!
他責の念が生まれる
人は他人に理由を押しつけたくなってしまう生き物です。
「私がいま貧乏なのは、親が貧乏だからだ!」というように、負の理由を自分ではなく他人に追い求めてしまいやすいのです。
役割が分断されると、個々のタスクが明確に自己の領域と他者の領域に分断されます。
しかし多くのタスクは、そうやって領域が分断されたものの、複数人が関わるものになります。
そういったときに、「このタスクが終わらなかったのは私ではなくあなたのせいだ」と、他責に転換しやすくなってしまうのです。
限定合理性が生まれる
限定合理性とは、一言で言うと限られた範囲内において合理的な判断をしてしまうことです。
例えば予算達成のために早く機能をリリースしたいPMと、技術的負債が溜まってリファクタリングをしたい開発チームの対立があったとします。
PMと開発チームはどちらもプロダクトの成功を目的にしているのは一緒です。
しかしそれぞれ自分の範囲内での合理性を発揮してしまっているため、同じ目的にも関わらず対立が起きてしまうのです。
役割を決めると、個々の担当範囲がどんどん細分化されていきます。
そのため限定合理性が生まれやすくなってしまうというわけです。
属人性が強まる
領域が固定化すると、当然のごとく領域ごとの属人性が強まります。
そのためタスクの偏りや、病気・退職などに対して脆弱性をもつ組織になってしまいます。
仕事をしないことにメリットが生まれる
仕事はやれば終わりではなく、基本的にやったあとのトラブル対応・保守などもつきものです。
そのため仕事を多くこなす人は多くの領域を担当するため、さらに多くの仕事をやらざるを得ない状況になってしまいます。
つまり仕事を頑張るほど忙しくなるという状況になります。
こういう体験をしてしまうことは非常に危険で、人間は楽な方向に流れるようにできてるものです。
そのような状態が長く続くと「いかに信頼を失わない範囲で仕事を押しつけるか」という方向に力学が働く危険性すらあります。
そうなると、仕事をゆっくり進めることや、あえてスキルを身につけず自分のできる領域を増やさないといったことに繋がりうるのです。
視野が広がらない
「父になって初めて親父の気持ちがわかった」なんて言葉にもあるように、何事もやってみて初めて見えてくることは多くあります。
しかし役割が限定されると、自ずと体験できる領域も狭まります。
これは他責の念にも繋がりやすく、人は知らないことに対して攻撃的になりがちです。
そのため役割を決めず同じ経験をすることは、相手の気持ちを理解しやすくなることにも繋がります。
一度体験するだけでも、その仕事の大変さ、やってくれてる人のありがたみがわかるわけです。
成長につながらない
役割が決められると、ほかの領域でほかの人がどのように作業をしているのかが見えづらくなってしまいます。
そのため「ほかの人のやり方から学ぶ」といったことが起きづらく、自己流になりがちです。
そうなると書籍などから自分で学習していくしか、成長の道はありません。
ですがこういった状況下において自分の作業がブラックボックス化するため、他者からのプレッシャーも薄くなります。
したがってそもそも自己学習していこうという気すら起きづらくなってしまいます。
コンフォートゾーンに逃げやすくなる
「他者の目がない」「成長しなくて良い」というのは、プレッシャーから解放された心地よい状況でもあります。
そのため、その状況になれるとそこから抜け出したくないという気持ちが生まれてしまいます。
さらに「成長をしない状態」が続くと、年齢に見合った能力が身につきません。
そのためどんどん「他者の目が介入しない状況」から抜け出せなくなってくるのです。
受け身になる
役割が固定化していなければ、目的に対して柔軟に考え、行動することができます。
しかし役割が固定化していると、何も考えずその役割だけをこなすだけになってしまいます。
役割が固定化した組織の解決法
それでは、役割が固定化した組織の解決法について考えてみます。
目標を明確化し、同じ目標を見る
まず前提として、全体での目標を明確化し、同じ目標を見るようにします。
個々の作業を可視化し、振り返る
誰がどのタスクを、どのくらい行ったか可視化します。
そして定期的に、それらについて振り返ります。
いわゆるアジャイルな方法論です。
これによりチームに対する貢献度合いが可視化され、仕事をしないことに対する監視の目が生まれます。
カオスエンジニアリングする
カオスエンジニアリングは、あえて不安定な状況を作って、正常な状態と比較することでシステムを改善していく手法です。
同じように組織もあえて不安定な状況を作ることで組織の問題を体感し、改善へ進めていくことができるようになります。
役割を固定化したことで起こる問題については、「1週間ある人が休暇を取る」「ランダムに担当を入れ替える」といったようなアクションを取ることで顕著化します。
そのため、あえてそのような状況を起こし振り返ることで、「Aさんが1週間いなくなっても良いように別の人がその範囲を担当しよう」といったようになります。
まとめ
というわけで、役割の固定化について考えをまとめてみました。
もちろん「専門性が増していく」といったような役割の固定化によるメリットもあるでしょうし、それが必要な組織もあるでしょう。
とはいえ役割の固定化はデメリットの大きいことであり、多くの組織にとって「それは避けるべきもの」だと私は考えます。